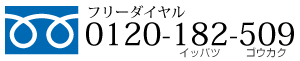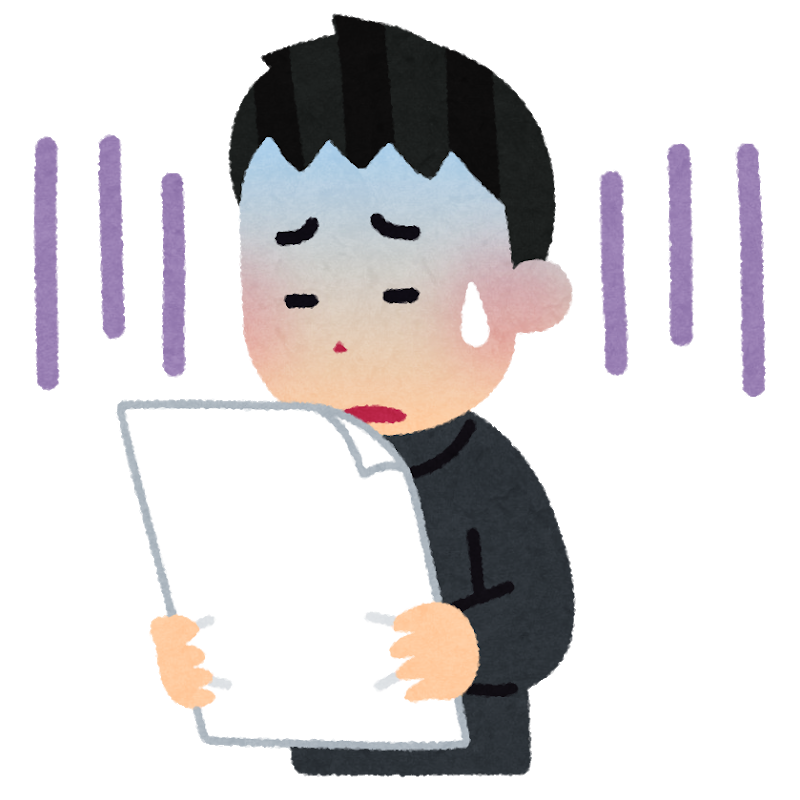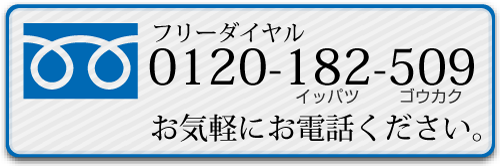皆さん、こんにちは!
寝屋川駅から徒歩2分、現役進学予備校ドリーム・チームの新田です。
今回は、高3受験生の『受験校決定から、スケジュールの組み方まで』を2回のシリーズでお話します。
ちょっと長いですが、本当に大切なことをまとめているので、
最後まで読んでくださいね!
受験決定からの大きな流れ
以前ブログにアップした主要私大の受験日程表からも、
関西では共通テストの1週間後、
1月末から2月中旬にかけて、五月雨的に毎日どこかの大学で試験を実施している状況です。
「受かるときは1回でも受かるし、ダメなときは何回受けても結果は同じだから…」
という声をよく聞きますが、
初めての大学受験で百発百中、自分の力を発揮するのはかなりの学力と精神力を要します。
ある程度土俵に立つ(=受験機会を確保する)ほうが、合格の確率は圧倒的に上がります。
私は次の①~③を生徒に確認した上で、12月に受験校決定面談をしています。
①第1志望校および併願校、特に滑り止め校は決まっているか
②浪人の可否
③合計で何回受験できるか
実例で説明しましょう!
サンプルは塾生のMさん、私立専願の法学部志望です。
面談前のヒアリングでは、
①第一志望は同志社大学で、併願校は関西大学と近畿大学を考えています。
②浪人はできません。現役での進学を考えています。
③1~2月期の受験で7~8回の受験までなら可能です。
とのことでした。
では面談スタート!
まずは写真のような表を書いたうえで、
受験予定校をそれぞれチャレンジ校・実力相応校・安全校に区分けして現状を見える化します。

チャレンジ校は文字通りチャレンジしたい大学、第1志望校ですね。
実力相応校は、「複数回受験することで、全滅するよりも1回以上合格する可能性が高い大学」と位置付けています。
安全校は所謂滑り止め校、模試でA判定が出る大学ということになります。
基準になる偏差値は、夏以降の全国模試の平均に、
多少の細工(大学の配点割合や現在の学力傾向)を加えて算出します。
Mさんの場合は3教科偏差値が56.1でした。
この基準偏差値の+5以上の偏差値帯がチャレンジ校、-7.5以下を安全校とします。
見たところ現状Mさんには安全校がない状態だと言えます。
浪人ができない状況で、これはかなりリスクがあります。
安全校を考える

多くの生徒にとって安全校はあまりピンとこないものですし、
どちらかというと考えたくないというのが本音でしょう。
自分の学力から2ランク以上幅を広げて考えることになりますので、
「えっ、そのレベルの大学まで受けないといけませんか…」ということになりがちです。
しかしセーフティネットをしっかりと張ったうえで受験することで、安心感が生まれるメリットも無視できません。
Mさんには、いくつかの大学を提案して検討するようアドバイスしました。
その際は受験科目が統一されていることが必須です。
対策の手間が少なくなり、出願費用も安くなりますので、
共通テスト利用も安全校対策としてはいいかもしれないですね。
受験校を決めるというのは大変な作業です。
場合によっては1時間以上、複数回面談することも稀ではありません。
受験する本人が最終的に納得して出願することが最も大切ですので、
そのために必要な材料をできるだけたくさん提供するように心がけています。
次の記事で具体的に受験スケジュールを組みます。
ぜひ、こちらもご確認下さい!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
現役進学予備校ドリーム・チーム(寝屋川市駅すぐ!)
大阪府寝屋川市八坂町14-17信越ビル2F
TEL:072-812-1077
mail:ngh-info@dr-t-eam.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~