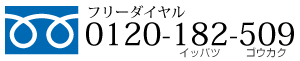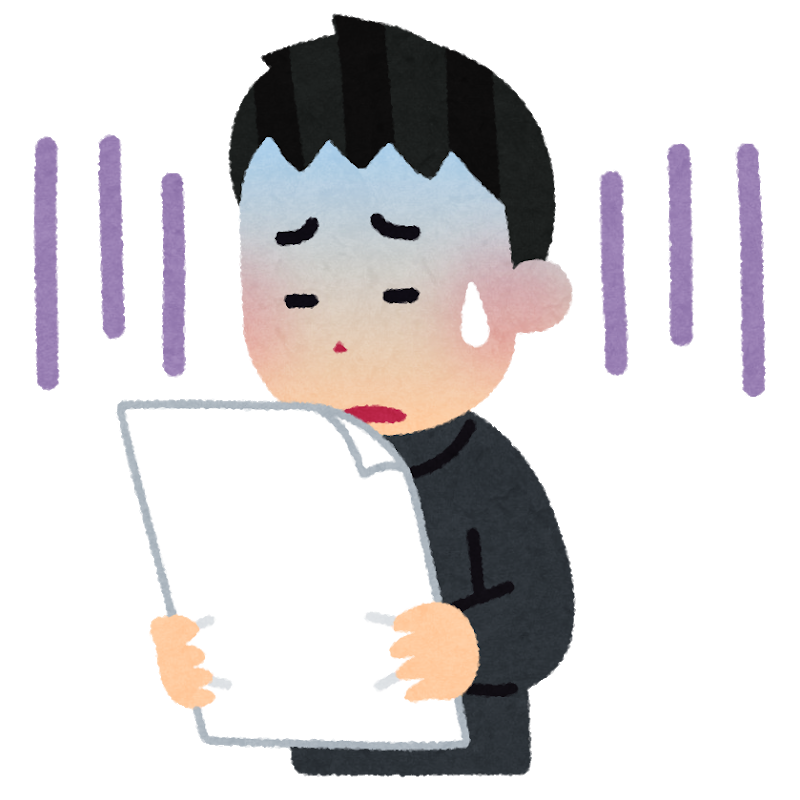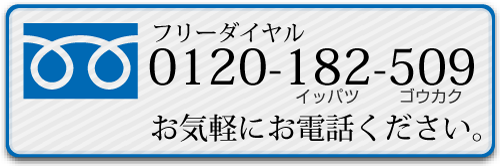共通テストにおける「英語民間検定試験」と「記述式問題」の導入が見送られる?
みなさん、こんにちは!
寝屋川駅から徒歩2分、現役進学予備校ドリーム・チームの新田です。
昨日WEBニュースをチェックしていたら、こんな記事が出ていました。
大学入学者選抜のあり方を検討する文部科学省の有識者会議は6月22日、2025年1月以降、つまり現在の中学3年生が受験する大学入学共通テスト(以下共通テスト)において、英語民間検定試験と記述式問題の導入について「実現は困難と言わざるを得ない」との提言案を示しました。 これを受けて文科省は今夏にも導入断念を正式に決定するとみられます。
えっ?まだそんなこと検討してたん?
もうとっくの昔に消えた話かと思ってた…
という人も多いでしょう。
2019年の12月、いまから1年半前の文科相による記者会見、
2020年度開始の共通テストにおいて、国語と数学の記述式問題導入を断念する
というコメントは記憶に新しいところです。
それ以降有識者会議において、継続的に審議されてきたわけですが、
この結論はある意味で既定路線だったかもしれませんね。
断念の主な理由として、
採点の質や受験機会の公平性が担保できない
が挙げられています。
社会の構造が変化し、それに伴って求められる人材も変わる中で、大学入試も変わらなければいけない!
知識偏重の詰め込み教育、一発勝負・1点刻みの学力評価を見直そう!
2011年から実質的な議論が始まった高大接続改革(高校教育の在り方と大学教育との接続)は、
掛け声はすばらしいが、それを実現するための制度設計が追いつけなかった
大山鳴動、ねずみ…
と総括されることになるのでしょうか。
共通テストで測るべき力は?
最初に結論を言ってしまうと、共通テストで測るべき力は、
「知識・技能」だと私は考えています。
みなさん、「学力の3要素」という言葉を聞かれたことはあるでしょうか?
これは、今から10年以上前に「学校教育法」という法律が改正された際に盛り込まれた、
今後の児童や生徒たちにとって「確かな学力を養っていくために必要な3つの要素」
という考え方です。具体的には、
知識・技能
思考力・判断力・表現力
主体性・多様性・協働性
の3つです。
ここでは細かい説明はしませんが、簡単にいうと
知識を身につけることのみに終始せず、
それを使って物事を深く考え、判断し、表現することで、
意見の異なる他者とも共により良い社会生活を送る力を身につけていく
ということです。
私は基本的にこの方向性に賛成です。
それまでの「ゆとり」がいいのか「詰め込み」なのかといった不毛(?)な議論に終止符を打ったんですから、
意義は大きいと思います。

ただこの基本方針を具体に落とし込んでいくのは並大抵ではありません。
高等学校ではアクティブラーニングで主体的な学びを実践することが求められ、
大学ではアドミッション・カリキュラム・ディプロマの各ポリシーを明示し、総合的・多面的な選抜方法が求められました。
そして「共通テスト」です。
記述式問題や英語外部検定試験の見送り以外にも学力の3要素を取り入れた作問が見られます。
複数の資料から必要な部分を判断し、比較しながら考える問題や
普段の授業風景や日常生活に関連させた設問など、
初期のセンター試験には見られなかった傾向です。
要不要を瞬時に判断する情報処理能力を求められる
設問が多くなっています。しかし、
思考力・判断力・表現力は、豊かな知識量がベースになくては身につきません。
すべてのもとになる知識・技能の到達度を測るのが共通テストの役目
ではないかと思うのです。
そのうえで各大学が個別学力試験において、求める学生像に合った力を測るのが自然ではないでしょうか?
設問形式にとらわれるあまり、深い学びに本来必要な基礎的学力を正確に測れないようでは、
それこそ本末転倒になってしまいます。
そういえば当初は、共通テストとは別に基礎学力を測る到達度テスト(仮称)を実施する案もありましたよね…
主役は受験生!
今回の有識者会議の提案には、「教育現場の声」や「若者たちの意見」なども反映されているとのことでした。
考えてみれば至極当然のことです。
ちょうど2年前、当時はまだ英語民間試験も記述式問題も導入される方向でした。
高校教員や予備校関係者からは、
民間検定試験導入は難しいんじゃないか?そもそも目的が違うテストでしょ?
記述問題の採点は学生がやるらしいよ。トラブルが目に見えてる!
などとネガティブな声ばかりだったように思います。
それでも当時の高2生は現代文の記述対策を必死にやっていました。

何でこんな年に生まれたんやろう…
ある生徒が口にした言葉は忘れられません。
「そのうち中止か延期が発表されるだろう…」
と思いながらも時間が過ぎていき、ギリギリのタイミングでの見送り発表に
一度動き出したものを止めるには、動き出させるのに必要な力の何倍もの力が必要になる
と恐怖にも似た感覚を覚えました。
目的は、生徒たちが将来の社会生活で役に立つ力を高校・大学教育で身につけること
その力を高校段階でどれくらい蓄積できているかを測るのが大学入試であること
を考えれば今後の方向性は自ずと見えてくるんじゃないでしょうか?
いつでもどんなときでも受験生が主役!ど真ん中において考えたいですよね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
現役進学予備校ドリーム・チーム(寝屋川市駅すぐ!)
大阪府寝屋川市八坂町14-17信越ビル2F
TEL:072-812-1077
mail:ngh-info@dr-t-eam.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~