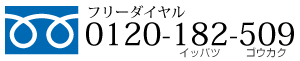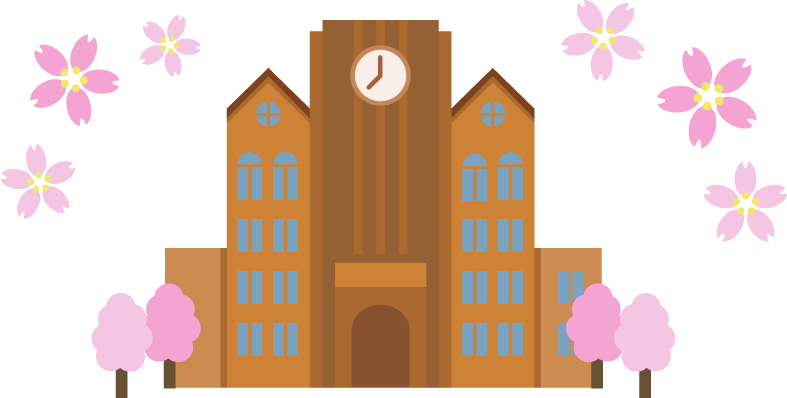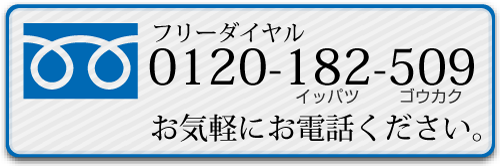こんにちは、ドリーム・チームの新田です。
雨ばかりでうっとうしい季節ですが、
高3生のみなさん、勉強してますか~?
いよいよ夏の全国模試が近づいてきました!
今回は模試についてのお話です。
うまく活用すれば、、、
成績アップのヒントがいっぱい!
使わない手はないですよね。
今日は、模試の意義や目的、活用方法をお伝えします!
今回、少し長文になっていますが、
貴重な情報もたくさん載せているので、最後まで頑張って確認してくださいね!

模試の意義① 模試は自分と志望校との距離を測る物差し
「まだ完璧に勉強ができてないから模試を受けても意味がない」
という声をよく聞きます。
合格可能性や判定は気になるところですが、
模試を受ける最も大きな目的は、
今の自分と志望校との距離を測ること、
結果を真摯に受け止め、
次へのステップにしてこそ受けた意味があるというものです。
結果から見えてくる具体的な点数(共通テスト換算得点)での志望校との距離、
そして〇点上げるんだったら何をどれくらいすればいいのか、
次に向けて「戦略」を練りましょう。
ここはぜひ塾に相談してくださいね!

模試の意義② 過去問演習は本気モードで!
模試の直前には過去問を解いて臨む人が多いと思います。
いくら基礎が固まっても、対策をしなければテストでは全く点数が出ないものです。
特に時間が厳しい共通テストでは形式に慣れておく必要があります。
それもただ10年分やるぞ!ではなく、
常に本番のつもりで、緊張感を持って取り組むようにしたいですね。
疲れるけどこれが大切!
そうすれば例えば国語で緊張のあまり(?)全く文章が頭に入ってこず、
「やばい…練習の時と違うよ~」と思った瞬間
文字が頭の上を流れていくだけ…みたいなことにはならないと思いますよ。
また、模試を受ける際には「解く順番」や「時間配分」も大切な要素です。
事前にシミュレーションしておきたいところですね。
そしていざ試験が始まったら、まず問題全体をざっと見渡して、
予定通りに進められそうか確認してから解き始めるくらいの「心の余裕」があれば完璧(?)です!!
模試の意義③ 夏の模試は「疑似本番」目標設定を明確に!
えっ?共通テストの本番は半年後でしょ?っていう声が聞こえてきそうですが…
私は夏の模試を本番の予行演習に位置付けています。
コツコツと基礎固めをしてきた皆さんは2学期以降に志望校の赤本を解き始めますよね。
逆算すれば「どの大学の赤本を解いていくか」を決定するのは“夏”、
つまりこの模試が基準になるんです!
次に目標設定です。
トータルの目標点を決めますが、この時「取れればいいなぁ~」の希望点ではなく、
これ以下なら志望変更かも?の必達点で決めるようにしましょう。
さらに各科目の目標点を決めるときにも気を付けてほしいことがあります。
例えばトータルで7割を目標にした場合、
全ての科目で7割を取る必要はありません。(当たり前ですが…)
入試は「総合力」の勝負、苦手科目で6割しか取れないのであれば、得意科目で補えばいいのです。
模試の意義④ 正答率で弱点補強を、成績統計資料はデータの宝庫!
ここからは模試を受けた後のお話です。
成績表と一緒に帰ってくる「成績統計資料集」って見たことありますか?
ここには、どんな問題で差がつきやすかったかや、
設問別の正答率なんかが載っています。
これが結構使えるんです!!
共通テストでは平均が5割程度になるよう作成されますが、
よく見ると正答率が10%程度の設問から80%近いものまで、
結構難易度に幅があるのが分かると思います。
一部の超難関大を除けば、
正答率の比較的高い問題をもれなく正解できればほとんどの受験生は目標点をクリアできるようになっています。
言い換えれば、目標点に届かないのは「みんなが正解できる基本問題を間違えた」か、
または「みんなが正解できない難問にこだわって時間をロスしてしまった」かの
どちらかの可能性が高いということです。
テストでは目標点を取ることが目的なのは先ほど書いた通りですが、
満点を取りに行ってしまって、
結果5割しか取れないような(大きなざるで金魚をすくうような)受け方は
残念としか言いようがありません。
もう一度自分の正誤表を見返してみてください。
きっとあるはずですよ!上達のヒントが!!

模試の意義⑤ 復習っていつやればいいの?
皆さん、エビングハウスの忘却曲線って聞いたことありますか?
せっかく勉強をしても復習をしなければ、人間の脳は必要ないと
判断してどんどん忘れていってしまうっていうものです。
だから復習をして長期記憶に蓄えられるようにしましょう!
という趣旨ですね。
効果的な復習のタイミングについては諸説あるようですが、
私も復習はとても大切だと考えていて、模試についていうと最低3回はやるように指導しています。
まず模試の当日か翌日に1回目の復習をすること。
テストでは知らない単語や、忘れてしまった公式、覚えたつもりの歴史年号など様々な「課題」に出会います。
もちろんテスト中は参考書など調べるわけにはいきませんから、何とかして答えを出そうと頑張りますよね。
これは脳が情報を欲している状態、一種の飢餓状態なんです。
ここで復習をすることによって得られた情報はより定着しやすいといわれています。
2回目は成績表が返却されるタイミング、多くは1か月後くらいですね。
ここではやり直しと併せて先ほど書いた正答率と比較しながら進めるのが良いと思います。
さらに英語長文や古文などは精読を心掛け、音読によるクロージングもやってほしいと思います。
数学や理科などは間違った問題の類題を解くなど、結構時間をかけて丁寧にやるのが効果的です。
3回目は入試本番直前の時期です。
ここでは今まで受けてきた模試を通しで復習することをおすすめします。
大手の模試会社は年間数回の模試の中で、頻出事項や典型問題を散りばめて出題します。
つまりこれを通しでしっかりと復習することで、大事な個所を網羅的に学習できるということなんです!
こうやって効果的な復習のタイミングについて書いてきましたが、
私は結局のところ最も大切なのは復習の回数だと思っています(*´σ-`)
人の顔も、よほど興味のある顔(?)でなければ、
一回や二回見ただけではなかなか多くの人数を覚えられないですよね。
勉強も同じで、記憶はそれを見る回数に比例すると思います。
大切ことは折に触れて復習し続けること!ですね。
以上です、受けっぱになってる人や全く対策をせずに受けようとしている人は今からでも遅くないです、
ぜひ参考にしてみてください((´∀`))
ドリーム・チームでは、学習相談や進路相談を随時承っています!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
現役進学予備校ドリーム・チーム
大阪府寝屋川市八坂町14-17信越ビル2F
TEL:072-812-1077
mail:ngh-info@dr-t-eam.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~