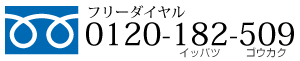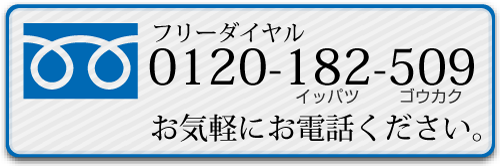こんにちは、京阪寝屋川市駅北口徒歩2分、現役進学予備校ドリーム・チームの新田です。
先月24日(火)読売新聞の投書欄「気流」に、次のような投稿が寄せられていました。
兵庫県の高校生からです。
というものですが、みなさんはどう感じられますか?
同年代の方なら
「めっちゃ共感できる!」
と思われるかもしれません。
予備校という環境で長く高校生を見てきた私には、
と同情に似た感情が起こってきました。
おそらく学校の先生は、
「覚えることは大切、でも覚えるだけで終わったらもったいない。 それをいろいろな場面で使えるように、知識として蓄えてほしい。 そのためには「なぜそうなるのか?」という意識(論理的思考) を持って覚えることが大切だよ。」
と言いたかったんだと思います。(違ってたらごめんなさい…)
「学力の3要素」という言葉を聞いたことがあると思います。
教育現場では新しい学習指導要領に基づいて、
「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・協働性」
という3つの要素を踏まえた指導が求められています。
これまでは、先生が生徒に向かって一方通行の授業を行い、
生徒はひたすらノートを取るという授業が中心でした。

また大学の入試問題においても、
覚えたものをそのままアウトプットさせる一問一答式の出題や、
重箱の隅をつつくようなある意味クイズのような出題が見られたことも事実です。
しかし、これからは学校の授業においてもITを活用したり、
グループワークを取り入れたりしながら、
社会で必要になる力を育てる方向にシフトしていきます。
みなさんが通う学校でも、いわゆる
アクティブラーニング形式の授業
が取り入れられているかもしれません。

一方で例えば英語を例にとると、
新学習指導要領では習得すべき単語数が大幅に増やされます。
さらにご存じのように
「聞く」「読む」「話す」「書く」の4技能
を総合的に学ぶことが求められます。
英文法においても単なる知識としてではなく、
実際のコミュニケーションの場での活用を想定して
指導するよう明記されています。
つまり、身につけなければならない知識量が増えた上に、
それらを活用できるレベルに底上げるために
多面的な学びが求められるわけです。
もうお腹いっぱい…という感じですね。

生徒はもちろんですが、
現場の先生方の苦労は計り知れないと思います。
同時に指導者の力量によって、
生徒たちの学力は大きく変わってしまうことも起こるでしょう。
冒頭の投書「知ることと覚えること」に戻ります。
「知る」というのは、勉強した結果「知らなかったことが知れた」「解けなかった問題が解けた」という自分の中に起きた変化に焦点を当てた言葉
「覚える」というのは、勉強するために必要な事柄や情報を自分の中にインプットするという動作に焦点を当てた言葉
だと思います。つまり、
覚えるという動作を起点にして、 覚えたことを用いて勉強し、 その結果としていままで知らなかったことを知ることで、 自分の中に変化を起こすことができる
という理屈ですね。換言すれば、

たくさん覚えるということは、 それを道具として活用し、 より多くのことを知る可能性を広げてくれる
ともいえるのです。
投書を寄せてくれた兵庫県の高校生には、
と伝えたいと思います。
現役進学予備校ドリーム・チームでは、
知識・技能の習得を強力にサポートします!
ぜひ無料体験授業にご参加ください!!
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
現役進学予備校ドリーム・チーム(寝屋川市駅すぐ!)
大阪府寝屋川市八坂町14-17信越ビル2F
TEL:072-812-1077
mail:ngh-info@dr-t-eam.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~