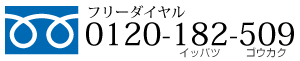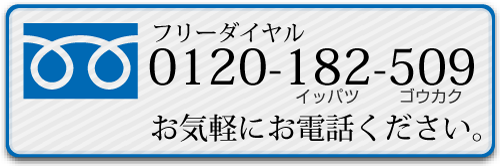みなさん、こんにちは!
寝屋川駅から徒歩2分、現役進学予備校ドリーム・チームの新田です。
当塾でも夏期講習が始まり、高1・2生はそれぞれの課題、
学校の宿題だったり1学期の復習だったりに取り組んでいます。
また3年生は8月の模試に向けて、基礎固めの最終段階に入っています。
中には共通テスト演習を10年分以上こなしている強者もいたりで、
みなそれぞれ暑い夏真っ盛りです!

言葉は生き物
先日SNSを使っていた時のこと、突然「りょ!」とメッセージが来ました。
前後の流れから「わかった!」という意味だと理解したのですが、「りょ」って…
と思って、「どういう意味?」と聞き返してみたら案の定、
「了解した」の意味でした。
驚いたことに最近は、同じ意味で「り」と返信することも多いとのこと、
ただの音やん?とツッコんでしまいました。
いかに短く、シンプルに表現するかがポイントだそうで…
「言葉は生き物、時代とともに変化していくものである」
とはよく言われますが、最近日本語が、
特に若者の間で変化しているなぁと思っていたら、
読売新聞の教育投書欄に次のような記事が載っていました。
「美しい日本語を守るには」というテーマに、
岩手県や栃木県の高校生のみなさんが意見を寄せる内容です。
「読書を通じて言葉に触れるべきだ」
「SNSを使わない交流の中で養うべきだ」
「聞くことで言葉に意識が向くのでは?」
「異なる世代との交流が大切だ」
など、どれもしっかりとした意見で感心しました。
文化庁が2019年におこなった「国語に関する世論調査」では、
若者言葉に乱れを感じると答えた人の割合が6割にのぼるとのことで、
「SNSとの適度な距離感が大切だ」と結ばれていました。
沈黙の螺旋
仲間内でしか通じないような言葉が生み出されることに危機感を持つ反面、
(自分もかつてそうであったように)若者ってそういう言葉を使いたい世代だとも感じました。
大事なのは、というか最も危惧されるのは、
独善的で、視野が狭く、限定的なコミュニティに安住して疑わなくなる
ことかもしれません。
SNSが身近になるにつれ、
自分と価値観の近いコミュニティでのみ生活していくことが可能になりました。
おすすめ記事はすべて自分の関心のあるものばかり。
自分と同じ意見のオンパレードは、あたかもそれが客観的なもので、
世間の大勢(=正義)のように感じて疑わなくなってしまうのは恐ろしいことです。
人間は、特に日本人は横並び意識が強いので、
あれっ何か違うんじゃない??
と感じたとしても、大勢に抗うことなく沈黙してしまう傾向があるといわれます。

社会心理学者の橋元良明氏は著書「ネットワーク社会」のなかで、
「沈黙の螺旋(らせん)」と表現しています。
みんな違って、みんないい(金子みすゞ)
「多様性」は、連日のメダルラッシュに沸くオリンピックの主要テーマです。
自分とは違う意見に耳を傾けながら、自分の考えを構築していく
これは、ハッキリ言って面倒で重労働です。

シンプルでわかりやすさが重視される現代においては、
少々時代遅れなのかもしれません。
しかし、このプロセスこそが
本当の国語力を養うんじゃないかとも思うのです。
「優柔不断な思考」を取り入れてみてはいかがでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
現役進学予備校ドリーム・チーム(寝屋川市駅すぐ!)
大阪府寝屋川市八坂町14-17信越ビル2F
TEL:072-812-1077
mail:ngh-info@dr-t-eam.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~